Essay 2
ミントティーを待ちながら
SCROLL

ホテルの方による一階から屋上までの館内アテンドを終えて、部屋に残された僕は、ひとり窓の外を眺めていた。これから二泊三日の滞在をする。だけど正直、少し圧倒されていた。フロアを移動するたびに異なる景色が現れることに。輝くらせん階段、上質な中庭、窓から見える横浜ベイブリッジ、海、水平線、そして使われなくなったハンマーヘッドクレーン……革張りの家具のなかには冷蔵庫が隠れている。

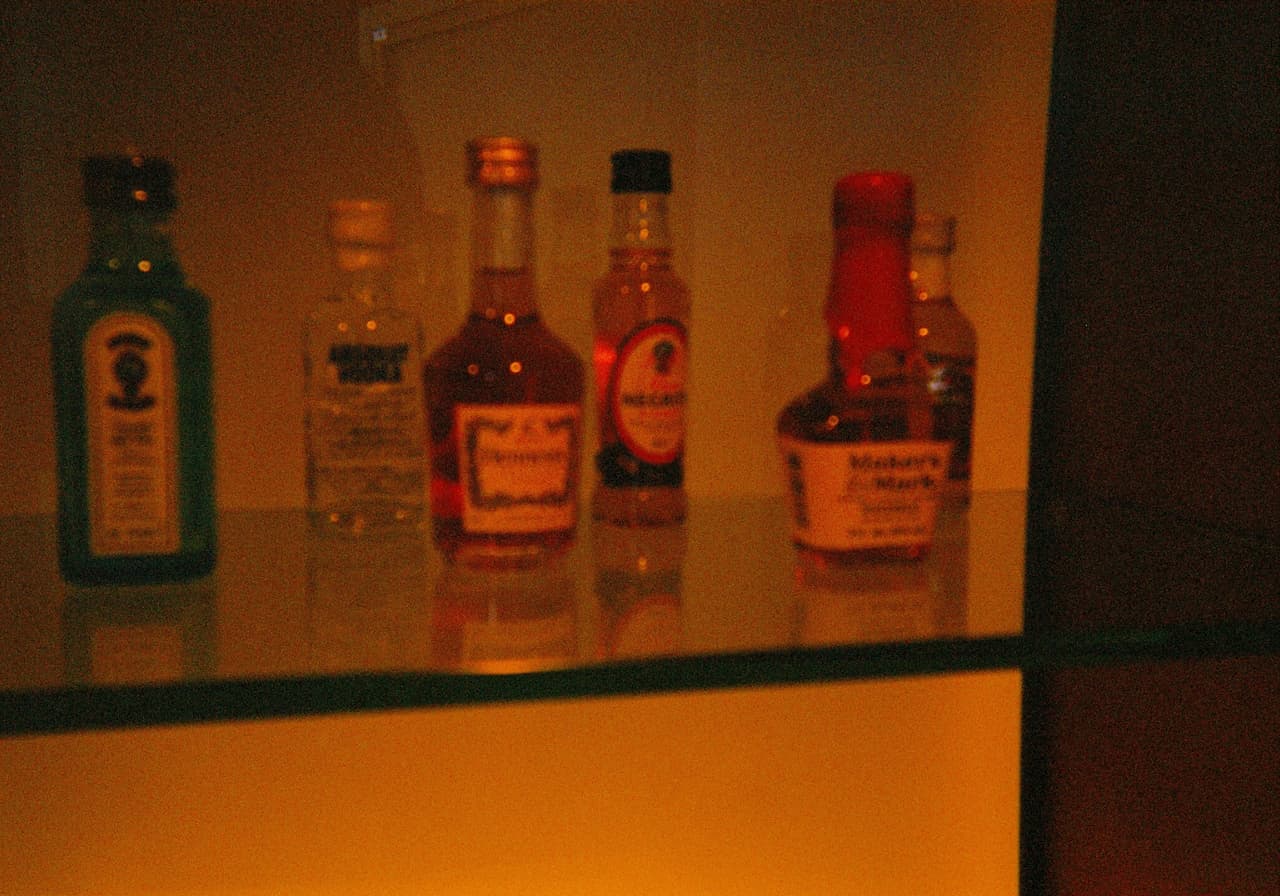
これまで、アーティストとして各地の美術館やギャラリーでの作品展示を生業にしてきた僕は、ホテルに滞在することも多かった。しかし僕がこれまで泊まってきたのは、あくまで「寝るため」のホテルだった。美術館の透明感とは無関係に質素なビジネスホテルに滞在することが多かった。
でもここは違う。まだ夕方だというのに、部屋から出るのがおっくうになっていた。めんどくさいのではない。もっと部屋と触れ合っていたいと思ってしまうのだ。横浜の埠頭に建てられたホテルは部屋から出たくなくなるような魅力に満ちていた。両手いっぱいに開いた窓から外の空気と光が入ってくる。
窓辺のソファーに座って黄昏れていた。
そういえば……と、僕に先立ってホテルの滞在記を書いた小谷さんが「ミントティーがすごく美味しかった」と言っていたことを思い出す。リモコンでテレビを操作してルームサービスから注文をする。到着の時間を選ぶことができたので90分後を指定する。部屋から出た後に、部屋に戻ってくる理由が欲しかったから。
エレベーターで一階に降りる。ホテルは埠頭の上に建っているので周囲は海である。
「海に近づいても不思議と潮の匂いがしない感じは、なんだか横浜らしいな」と考えながら歩いていると、それでも少しだけ海が香る。なんとなく赤レンガ倉庫の方へ行ってみることにした。でも芝生と街路樹がそこかしこにあるので直線では向かえない。犬の散歩をする人を追い抜く。ランニングする人が僕を追い抜く。緩やかなカーブを描きながら歩く。釣りをしている人がいる。傾いていく太陽に照らされながら色を変えていく景色が美しすぎて、なんだか建物のなかに入るのがもったいなく思えて、草木の写真を撮ったりしながら近くのベンチから海を見る。


こんなにゆっくり時間を過ごしたのは、いつぶりだろう? いまの僕がすべきことは、自分の部屋にミントティーが運ばれてくるまでのあいだ散歩することだけである。贅沢にも、音楽を聴くかどうかで悩んでみたりする。普段聞かない洋楽でも、と思って、昔母親に教えられたジェフ・ベックをイヤホンから流す。
部屋に戻ると、すぐにミントティーが運ばれてきた。思っていたよりもたっぷりあったので、とりあえずカップ一杯分だけ飲むことにする。最初はストレートで風味をたのしんで、後半は砂糖を入れてたんと甘くした。窓の外で太陽が沈んでいくのを感じたけれど、僕の部屋は東向きだった。日没が見える場所に行きたくて屋上にあがる。なんて自由なんだろう。
だけど屋上も東向きだった。背伸びすると植物の隙間から西日が見えるけれど、もう少しでここも日陰になるんだろう。産業遺産であるハンマーヘッドクレーンだけは、もう一度見ておきたいと思ったので屋上をぐるりと巡ると、フランス語を話す老夫婦がソファーでくつろいでいた。それを横目に巨大なクレーンが動いていた日を想像する。


かつて工業地帯だったという周辺地域は、1960年代後半から開発がはじまって、現在のように人々が集う場所になったのだという。
今回の滞在に先立って、そんなことを調べていた。実はこの滞在が終わった翌日から横浜市民ギャラリーという施設での展示がはじまるのだ。本当にたまたまなのだけど、明日の昼も搬入に行くし、残された作業もある。でも一旦そんなことは忘れて横浜の歴史に想いを馳せていた。なんといっても、今回つくった作品は横浜をモチーフにしたサイエンスフィクションなのだ。その作品を完成させるための最後の一手に向けて産業遺産を眺める時間は無駄じゃない。
そうして景色を眺めながら、この埠頭に来たことがあることを思い出した。いまホテルが建っている場所には、母校である東京藝術大学の大学院映像研究科のキャンパスが建っていたのだ。僕が入学したときには、埠頭から横浜中華街へと校舎が移転していたのだが、かつての真っ白い撮影用スタジオやギャラリーがあった頃も、今も、変わらずにハンマーヘッドクレーンは立ち続けている。工業地帯だったり、大学だったり、ホテルだったり。街は何度も生まれ直す。
西日を見るためにランドマークタワーの方へ向かうことにした。円形の歩道橋である新港サークルウォークをつたって交差点を越える。サークルウォークには周辺の歴史や、過去の景色を伝えるパネルが展示されていた。足元で高速道路へと吸い込まれていく車が見える。気がつけば街灯が光りはじめていた。
オレンジ色の空に照らされていても、みなとみらいはグレーに感じられた。別に色が無いわけではない。だけどいつもグレーに感じられるのだ。
思い出すのは小学校の図工の授業での出来事である。クラスメイトと一緒に、十二色すべての絵具を、それぞれのパレットへとチューブから少しずつ出して、かき混ぜた記憶。僕がグルグル回す筆によって赤や青が細長く混ざっていって、元の色が見えなくなり、最終的には黒っぽい茶色になる。しかし友達のパレットを見てみると、同じチューブから絵具を出したはずなのに、僕と違って綺麗なグレーになっていた。

三原色を均等に混ぜるとグレーになる。当たり前のことだ。しかしバランスが悪いと茶色とか緑に偏ってしまう。偏りなく色を揃えるには計画性が必要だ。偶然に身を任せるのではなく、丁寧にひとつずつ色の量を選ぶ必要がある。たぶん小学生の僕は大雑把だったのだ。でも、だからこそ、横で綺麗なグレーをつくることができるクラスメイトを羨ましいと感じた。そういった色彩のハーモニーをみなとみらいを歩いていると思い出すのである。ジェットコースターも、レンガ造の建物も、走り回る車も、街灯も、すべてが別様に色づいている。だけど街全体で眺めるとグレーに思える。そんな景色の調和は横浜ならではだ。

徐々に空から色がなくなっていく。そういえば二階のレストランでのディナーを予約してもらっていた。ランドマークタワーの中を通過して、横浜美術館を越えて、パシフィコ横浜の前を通ってホテルに戻る。
ディナーはコースになっていた。前菜を通過して、レモンドレッシングのカルパッチョが運ばれてくる。水だけでは物足りないので戦前の横浜で生まれたというカクテルをオーダーする。すべてが繰り返し味覚をゼロから生まれ直させるような新鮮な美味しさだった。冷たいスープと温かいパン。夜の闇に染まった窓に自分の姿が映り込んでいる。すべての所作が優しくなってしまう。次々と料理が運ばれてくる。


なんだか、少しだけ、泣ける。
アーティストなんてのは、職業としては、そんなにキラキラしたものではない。独りで本を読んで、絵を描いて、映像を編集したりして作品をつくっていくわけだけど、もちろん常に褒められるわけではなく、寝ずに頑張っても上手くいかないことも多い。それでも美しいものをつくらなければならない。二十歳の頃から自主企画を中心に活動してきて、ここ数年で誰かが仕事を依頼してくれるようになった。使ってみたい素材や機材を買ったり、少しだけ高い珈琲を飲んだりできるようになった。しかし経済的にも技術的にも誰かに支えてもらえるアーティストは一握りである。その現実を思い出して、現状に対して感謝しつつ、運ばれてくる黒毛和牛のポワレをナイフで切る。添えられたトリュフと一緒に口に運ぶ。

ホテルでディナーを食べる僕はガラスに反射していた。まるでインスタグラムのフィルターのように、窓の外で揺れるイルミネーションが僕のシルエットと重なり合って、輝いていた。それは一瞬の虚構である。だけど綺麗でうれしかった。そういう瞬間がある人生で良かったと思う人間が僕だった。
二年ほど前、東北の小さな飲み屋で知り合った中年の男性がいた。数年に一度奮発して夫婦で旅行に出かけるのだと嬉しそうに語っていた。かつては横浜に行ったこともあると言っていたように思う。そんな旅の魅力を、その時点ではあまりよく分かっていなかった。だけど今回滞在したなかで、やはりこうやって自分がキラキラする時間を愛おしいと思った。
また料理が運ばれてくる。ひとりなのに一時間以上かけて最後まで食べた。
この世界のどこかに自分の家があって、自分だけの部屋があって、机があることはとても豊かで心を落ち着けてくれる。だけどそれだけではなく、僕たちは、旅に出ることができる。旅のなかで見つける幸せとは、ミントティーが運ばれてくるまでのあいだの目的のない散歩だったり、窓に映った自分が光っていることだったりするのだろう。そのなかで色々なことを思い出すのもまた、旅の魅力に思える。
翌日、僕は朝からギャラリーへと搬入に向かった。そのギャラリーは今年で60周年を迎える。つまり横浜が、工業生産の街から、現在のように人々のための街に生まれ直す時代につくられた場所だ。一日かけて作業して、またホテルに戻る。
そして湯船に全身を浸からせる。浴室はガラス張りなのでベッドルームのテレビを見ることができる。横浜が生まれ直していた1960年代につくられた洋画を観た。次はもっともっと目的のない旅をしてみよう。そう思いながらピンとした白いシーツをかき分けてベッドのなかに潜り込んだ。
最後の朝は、驚くほど早起きしてしまった。するとベッドルームが東向きだから太陽が昇るのが見える。ベイブリッジの光と朝日が重なっていく。フィルムカメラに写るのか分からないけれど、そんな朝日に向かって二度シャッターを切った。そこに何かが写っていても、いなくても、その分からなさ自体が「ここを訪れた思い出」になってくれたらと願いながら。


PROFILE

アーティスト
布施 琳太郎
RINTARO FUSE
1994年生まれ。スマートフォンの発売以降の都市における「孤独」や「二人であること」の回復に向けて、自ら手がけた詩やテクストを起点に、映像作品やウェブサイト、展覧会のキュレーション、書籍の出版、イベント企画などを行っている。主な活動として個展「新しい死体」(2022/PARCO MUSEUM TOKYO)、キュレーション展「惑星ザムザ」(2022/小高製本工業跡地)など。著書として『ラブレターの書き方』(2023/晶文社)、詩集『涙のカタログ』(2023/パルコ出版)。
宿泊した客室

クラシック ヨコハマハーバービュー
1ベッド(ダブル)
Instagram投稿キャンペーン
(7月26日 – 8月26日)
インターコンチネンタル横浜Pier 8公式Instagramアカウントをフォローのうえ、「ふと、埠頭で」エッセイの感想に当ホテルアカウントのメンションをつけてストーリーズに投稿いただくと抽選で宿泊券をプレゼントいたします。
インターコンチネンタル横浜Pier 8公式アカウント:@icyokohamapier8




